「先生って、授業以外は何してるの?」
「職員室ってどんな雰囲気なの?」
「うちの子のクラス替え、どうやって決まったの?」
小学校の先生の仕事について、気になることはたくさんあるのに、なかなか聞く機会がないですよね。
実は、小学校教師の仕事は想像以上に多岐にわたります。朝7時過ぎには学校に到着し、夜7時、8時まで残ることも日常茶飯事。授業はもちろん、生活指導、保護者対応、学校運営、地域活動まで…その仕事量は膨大です。
私は元小学校教員として12年間、1000人以上の子どもたちと向き合ってきました。
その経験から、普段は見えない「小学校教師のリアル」を、本音でお伝えします。
この記事では、小学校教師の1日の流れから、クラス替えの裏側、通知表の評価方法、いじめへの対応、職員室の人間関係まで、保護者の方が本当に知りたいことを包み隠さずお話しします。
この記事を読めば、
・お子さんの担任の先生がどんな1日を過ごしているか
・学校での出来事の背景にある先生の思い
・先生とより良い関係を築くためのヒント
が分かります。
先生の仕事を理解することで、学校と家庭の連携もスムーズになるはずです。ぜひ最後までお読みください。
小学校教師の仕事内容は?
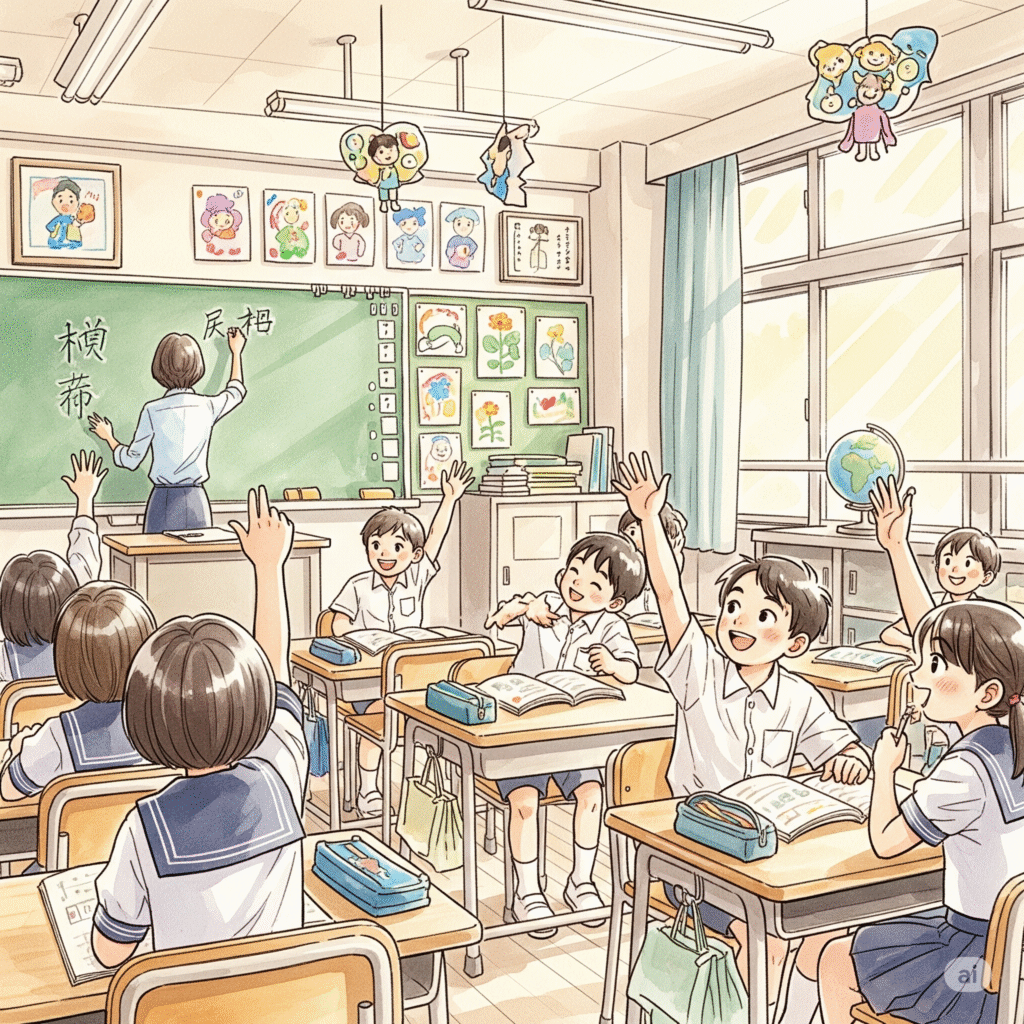
教科指導
授業をするのが最も多い業務です。
小学校では、担任教師が国語や算数など主要教科を幅広く担当します。
黒板に向かって「10ページの問題を解いてみよう」と声をかけたり、グループでの話し合いを進めたり。
授業だけでも1日4〜5コマあります。
宿題の準備やテストの採点も含まれるので、授業時間以外の負担も大きいのです。
生活指導や道徳教育
学校は「勉強する場」であると同時に、「社会性を育てる場」です。
登下校時には挨拶の声かけ、授業中にはルールを守る指導、休み時間には友達関係のトラブル解決など。
運動会や学級活動などの行事も生活指導の一部です。
特に小学校では「学ぶ力」だけでなく、「生きる力」を育てることが求められています。
保護者との連携
授業が終わってからも、保護者とのやりとりがあります。
懇談会や家庭訪問、連絡帳でのやり取りなどを通じて、学校と家庭の橋渡しをします。
「家では勉強しないんです」「友達関係が心配で…」といった相談を受けることも多く、その対応次第で子どもの学校生活が大きく変わります。
学校運営や地域活動
教師の仕事はクラスだけに留まりません。
職員会議や委員会活動、運動会や卒業式の企画・準備など、学校全体の運営に携わります。
さらに地域の行事や防犯活動など、地域とのつながりも大切にしています。
小学校教師ってどんな仕事?~教師の一日~
午前中
朝は7時過ぎに学校へ到着します。早い人は6時台から出勤しています。
- 朝の会やミーティングで1日がスタート
- 1時限45分の授業を担当
- 休み時間も子どもと遊んだり、宿題の採点をしたり
教師に「休み時間」はほとんどありません。子どもたちと関わり続けるのが実際です。
午後は?
- 子どもと一緒に給食を準備、片付け
- 清掃時間も一緒に活動
- 午後も2〜3コマ授業を行い、帰りの会で下校を見送る
子どもと同じ時間を共有しながら、学びと生活の両面を支えます。
子どもが帰った後に……
子どもが下校してからも教師の仕事は続きます。
- ノートや宿題の採点
- 翌日の授業準備
- 職員会議や研修参加
- 委員会やクラブ活動の運営
定時は17時頃ですが、実際には19時〜20時まで残ることも珍しくありません。
中学校・高校教師との違い
小学校は担任制が基本。
音楽や図工を除き、1人の担任が複数教科を教えるため、子どもとの関わりはとても密接です。
一方で、中高は教科担任制。専門性が高まる一方で、思春期特有の課題に向き合う必要があります。
小学校教師という仕事のやりがい
大変さも多いですが、それ以上にやりがいを感じる瞬間があります。
- 苦手だった算数が「できた!」に変わる瞬間
- 運動会で仲間と協力して達成感を味わう姿
- 「先生ありがとう」の一言で救われる日
子どもたちの成長を間近で見られるのは、教師ならではの特権です。
よくある質問
先生って、授業以外は何をしているの?
「授業が終わったら先生は何をしているの?」
多くの保護者から寄せられる質問です。
実は、子どもたちが下校してからが本当の忙しさの始まりなんです。
若い先生は、翌日の授業準備ノートや宿題の丸つけに追われています。
大変なクラスを担任している先生は、保護者と電話でやり取りをすることも。
学校によっては毎週のように職員会議や研修が入り、放課後のクラブ活動(中学校でいう部活)を担当する場合もあります。
さらに、自分に任されている校務分掌(研究主任や生徒指導担当など)もこなさなければなりません。
私自身、独身時代は夜9時を過ぎても職員室に残るのが当たり前でした。
結婚して子どもが生まれてからは、仕事の要領を工夫するようになり、ようやく19時ごろには帰宅できるようになりました。
ただ、中にはお菓子を食べながらだらだら仕事をする先生も…。
私はそういう先生を見ると、「子どもたちのために、もう少し頑張ってほしいな」と心の中で思っていました(笑)。
「クラス替え」や「席替え」って、どうやって決めているの?
「うちの子、座席(クラス)を配慮していただけませんか?」
保護者から、こんなお願いを受けることがあります。
実際には、座席やクラスは先生たちが細かく配慮して決めていることが多いのです。
- 子どもの性格
- 友人関係やトラブルの履歴
- 学習面や支援の必要性
- 学級全体のバランス
特にクラス替えは、職員室で何度も会議を重ねます。
私が経験したときも、
「この子にはあの子をつけておけば安心だ」
「ここは離した方がいい」
と先生同士で資料を用いて長時間話し合いました。
正直、クラス替えは神経をすり減らす作業です。
配慮を誤れば、翌年度そのクラスを担任する先生が本当に苦労するからです。
それでも、実際に始まってみないと分からない部分も多く、
「このクラスが想像以上に大変だった」と気づくこともありました。
中には、4月の段階でクレームを言いに来る保護者もいました。
席替えも同様に、黒板の見やすさや友達との相性を考慮して決めています。
単なるくじ引きやランダムではありません。
ただし、自治能力が高いクラスでは、担任の判断で子どもたち自身に座席を決めさせる場合もあります。
自分たちで責任を持って決める経験は、クラスづくりに良い影響を与えることもあります。
通知表の評価って本当に公平なの?
「先生によって甘い・厳しいってあるんじゃないの?」
こう感じる保護者は少なくありません。
結論から言うと、通知表の評価には共通の基準はありますが、先生ごとの見方に差が出ることもあります。
評価の仕方は時代とともに変化している
昔は、
- ノートをきちんと提出しているか
- 授業中に積極的に発言しているか
といった行動面が重視されていました。
しかし、今はそれだけでは評価してはいけないことになっています。
にもかかわらず、実際には昔ながらの方法で評価してしまう先生もいて、これが「先生によって差がある」と言われる理由のひとつです。
テストの点数だけで評価できない理由
テストはどうしても「活字を読み取って解答する力」に偏ります。
しかし子どもによって、学習の得意・不得意や表現方法は異なります。
だからこそ、普段の授業での発言やノートに書かれた記述など、多角的な視点で判断することが求められます。
実際に感じたこと
私も学年会で、
「この子はテストの点数は低いけど、授業中に真剣に取り組んでいる」
「努力をどう評価するか」
といった議論を何度も交わしてきました。
最終的に「努力をきちんと認める」という合意に至ることも多くありました。
担任によって差が出るのはなぜか
結局のところ、評価をどこまで広く取るかによって差が出ます。
- テスト点数重視型の先生
- 普段の取り組みを重視する先生
あなたのお子さんの担任は、昔ながらの基準で評価する先生ですか?
それとも、今の時代に合わせた多角的な評価をしてくれる先生でしょうか。
いじめの相談を受けたら、先生は実際どう動くの?
「子どもがいじめられているかもしれない」
そんな相談を受けたとき、先生はどう対応しているのでしょうか。
結論から言うと、先生はすぐに動きます。ただし、担任1人で抱え込まず、学年の先生や管理職と連携しながらチームで対応するのが鉄則です。
ただ、現場の先生の中には「自分のクラスで問題が起きたのは自分の責任だ」と強く感じ、相談をためらうケースもあります。それほどいじめ対応はプレッシャーの大きい業務です。
私自身も、これまでに何度もいじめ事案に関わってきました。
直接保護者から相談を受けたこともあります。その際には、まず本人や周囲の子どもから丁寧に話を聞き、すぐに学年の先生や管理職と情報を共有しました。
場合によっては、授業をすべて自習にして、1日かけて聞き取りを行うこともあります。その際は管理職と綿密に打ち合わせをし、誰から聞くか、どんな順番で話を進めるかまで決めて対応しました。
あるケースでは、いじめが原因で学校を休んでいる児童の家庭に訪問し、直接話を聞いたこともあります。
いじめ対応で最も大切なのは スピード感。
放置すれば一気に深刻化してしまうため、「その日に判明したことはその日に解決する」 という意識で動く必要があります。
保護者の方へお伝えしたいのは、**「早めの相談が何より大切」**ということです。先生は一人で抱えるのではなく、学校全体で子どもを守る体制を取っています。どうか迷わず相談してください。
職員室の先生同士の人間関係ってどんな感じ?
「先生同士って仲がいいんですか?」とよく聞かれます。
結論から言うと、学校によって大きく違います。
まず、職員室の雰囲気を最も左右するのは管理職です。
管理職同士の関係や、管理職と職員の関係が良好であれば、自然と職員室全体の雰囲気も良くなります。これは、子どもと先生の関係がクラスの雰囲気を作るのと同じです。
しかし、逆に管理職との関係が悪いと、陰口や噂話が広まり、派閥が生まれることも。
私も実際に、愚痴を聞かされるのがしんどかった経験があります。
さらに、小学校は女性教員が多い職場です。そのため、いわゆる「お局先生」が存在する学校もあります。私もお局に出会ったことがあり、ゴマをすって嫌われないように必死でした。嫌われれば、どんな陰口を言われるかわからない…それが現実です。
ただし、忘れてはいけないのは、先生たちは最終的に「子どものために」という目的で一致しているということ。 多少の人間関係の難しさがあっても、いざ子どもに関わる場面では一致団結して対応します。 「これ手伝ってもらえませんか?」と声をかけるとみんな快く動いてくれます。 優しくて親切な先生が本当に多いです。 つまり、職員室は人間模様が複雑ではあるものの、出会いは一期一会であり、協力して子どもを支える場でもあるのです。
まとめ
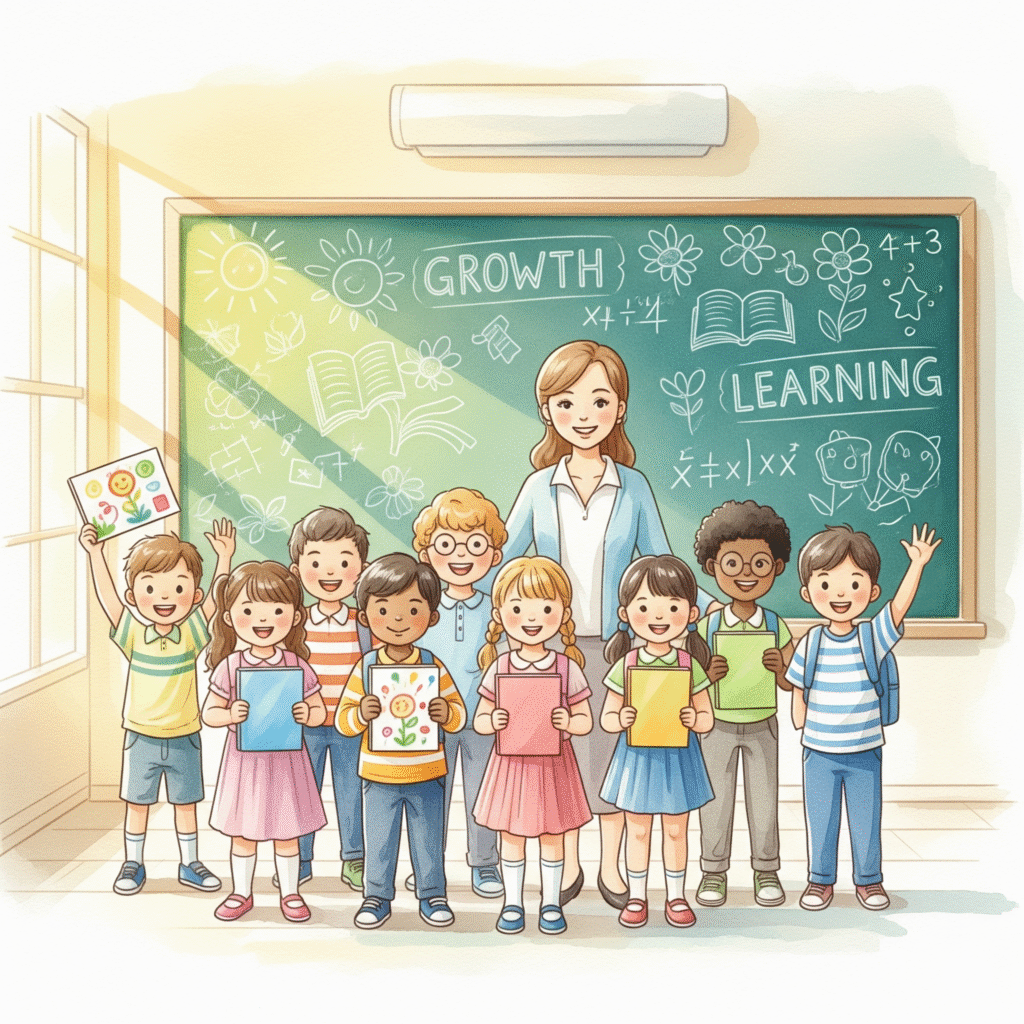
小学校教師の仕事は、授業だけでなく生活指導、保護者対応、学校運営など多岐にわたります。朝から晩まで子どもたちのために働く先生たちの姿を知ることで、学校への理解も深まるはずです。
クラス替えや席替え、通知表の評価など、一見シンプルに見えることも、実は先生たちが子ども一人ひとりを考えて決めています。 いじめ対応では学校全体でチームとなって動き、職員室では複雑な人間関係の中でも「子どものため」に協力し合っています。
先生も人間です。大変なことも多いですが、子どもの成長を間近で見られるやりがいを感じながら日々奮闘しています。
この記事を読んで「小学校教師のリアルな仕事内容」を知ることで、保護者の皆さんも先生をより理解でき、学校との連携がよりスムーズになるでしょう。

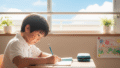

コメント