読書感想文を書くときに「何から始めればいいの?」と悩んでいませんか。実は、読書感想文の出来は本選びの段階でほぼ決まってしまいます。自分の体験や興味に関連した本を選べば、書きたいことが自然とあふれ出し、充実した感想文が書けるようになります。
この記事では、元教員の経験から導き出した、読書感想文を上手に書くための4つのステップを詳しく解説します。「〇〇を読んで」という平凡なタイトルから脱却する方法、「〜と思う」を使わない表現テクニック、あらすじの効果的な織り込み方など、すぐに実践できるコツが満載。
付箋を使った読書法や親子での対話を通じた感想の引き出し方など、スムーズに書き進めるための工夫も紹介します。読書感想文が苦手な子どもでも、楽しく取り組めるようになるでしょう。
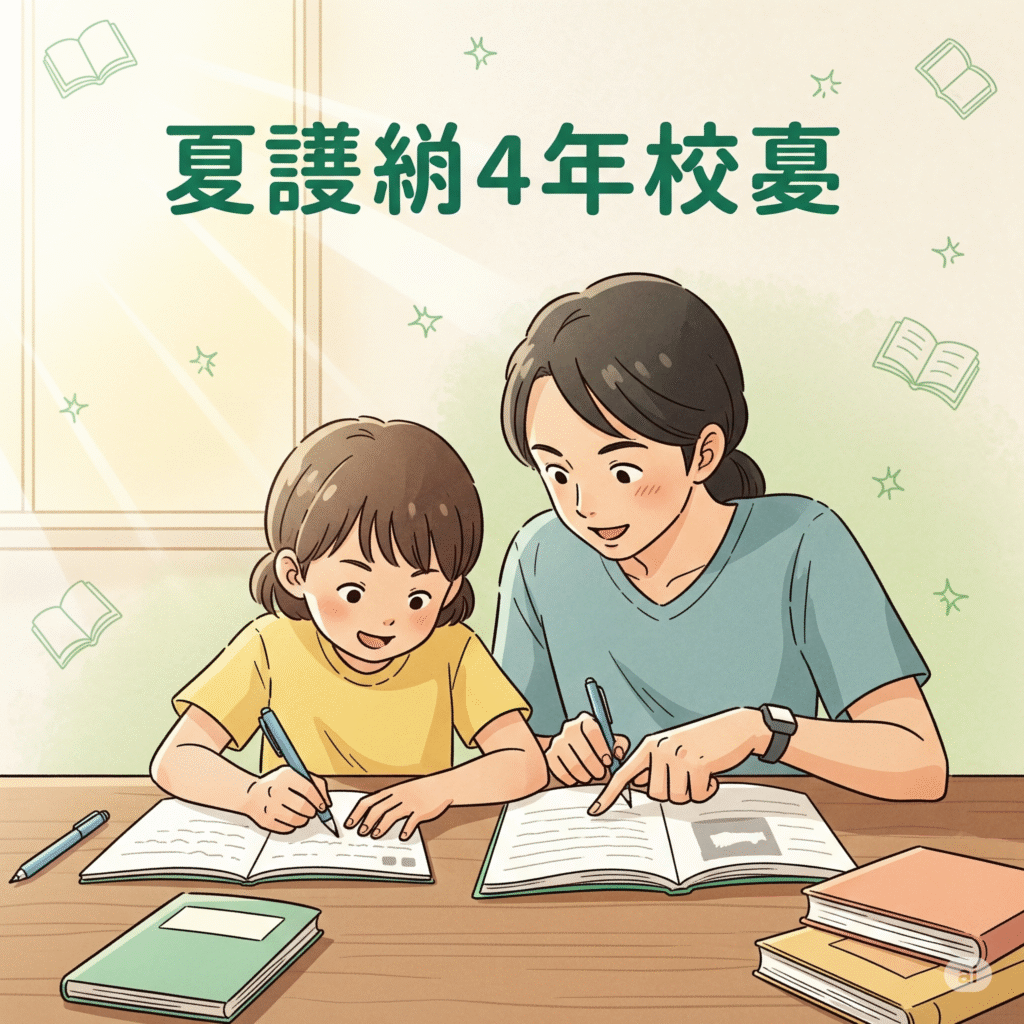
読書感想文の成功は本選びで決まる!4つの執筆ステップ
読書感想文を書くとき、何から始めればよいか悩む人は多いでしょう。実は、本選びの段階で読書感想文の良し悪しがほぼ決まります。自分が体験したことや、普段から関心を持っていることに関連した本を選べば、書きたい内容が自然とあふれ出し、充実した感想文になります。
このページでは、読書感想文の書き方を4つのステップで分かりやすく解説します。読書感想文が苦手な子どもでも、スムーズに書く力を身につけられるテンプレートも紹介しています。夏休みの宿題で読書感想文を書く際、時間に追われると子どもも保護者もストレスを感じてしまいます。質の高い読書感想文を仕上げるには、事前の準備が重要です。
読書感想文を上手に書くための4つのステップ
※ここでは原稿用紙の使い方などには触れません。あくまで読書感想文の内容に焦点を当てます。各都道府県によって独自のルールがある場合もあるため、原稿用紙の使い方が分からない場合は、学校の先生に確認することをおすすめします。
ステップ①:ありがちなタイトル「〇〇を読んで」から脱却しよう
読書感想文の執筆をスタートする際、まず迷うのがタイトルの決め方です。 悩んだ末に「〇〇(書名)を読んで」という無難なタイトルにした経験がある人は多いでしょう。私もその一人でしたが、今思えばもったいない選択でした。
タイトルに独自性があるかないかで、感想文全体の印象が大きく変わります。 「この感想文は興味深そうだ」「独自性がある」と読者に思わせることができれば、最初の関門はクリアです。
多少の演出でも構わないので、タイトルで読み手の心をつかみましょう。独創的なタイトルを先に考えれば、書きたい内容が浮かびやすくなることもあります。逆に、感想文を完成させた後でタイトルを考える手法もあります。決まりはないので、自分に合った方法を見つけてください。
例えば『ハリー・ポッター』の読書感想文なら:
- 「魔法界の真実、お教えします」
- 「魔法の杖なんて必要ない」
- 「呪文を最も効果的に活用する手段」
- 「魔法は人を堕落させる」
- 「ハリーvs私」
「最も〜」や「〜する手段」「〜お教えします」という表現は、読者の興味を惹く文句として有効です。「必要ない」「堕落させる」といった否定的な表現は、手軽にインパクトを与えられます。
ただし、多用すると悪い印象を与える可能性があるので注意が必要です。否定的なタイトルとは対照的に、内容は積極的で、本を読んで自分がどう変化できたかを書けば、良いコントラストが生まれ、印象的な感想文になります。
タイトルと同じくらい重要なのが、「一文目に何を書くか」です。
例えば、セリフから文章を始めるのも効果的です。「出れんの?」という言葉から始まる作文を書いた経験があります。市の陸上大会2日前に骨折し、涙を流しながら医師に訴えた言葉でした。このように、印象的な一言から始めると、読み手の心をつかめます。
ステップ②:「〜と思う」を使わない表現で差をつける
すでにご存じの方も多いと思いますが、これは本当に重要なポイントです。 「絶対に」というのが肝心で、「〜と思う」の代わりに使える表現をどれだけ知っているかが重要になります。
日頃から読書をする子としない子では、このような場面で表現の幅に差が出ることもあります。 日頃それほど読書をしない子でも、人との会話やテレビなどで、他人が何気なく使った「使えそうだな」という言い回しや表現を覚えておくと役立ちます。
私が「〜と思う」の代わりによく使う表現は以下のとおりです。
- 〜と感じる、〜のように感じられる
- 〜だと想像した
- 〜という感情になった
- 〜という結論に達した
- 〜ではないだろうか
- 〜に違いない
- 〜と確信した
単純に物語を味わうだけでなく、作家が「〜と思う」の代わりにどのような表現を使っているか注目して読むのも興味深いです。「この作者はこうした表現をよく用いる」「同じ内容を描くのに、作者によって手法が完全に異なる」といった気づきも、読書の醍醐味の一つです。
ステップ③:あらすじは最小限に、自分の考えに織り込む
あらすじを入れるべきか入れないべきかは、意見が分かれるところです。 私の考えでは、読み手の立場に立つと、知らない本については、ある程度のあらすじや本の内容を把握していた方が格段に読みやすいと思います。
そのため私は、読み手が感想文に入り込みやすいように、あらすじを織り込む派です。ただし、あらすじは最小限に抑えたいというのが本音です。あらすじを入れなくても、本の内容が読者に伝わるような文章が理想的です。
あらすじを入れるというより、読者にも物語の展開が分かるように、補足情報を加えるつもりで書くのがポイントです。
再び『ハリー・ポッター』で読書感想文を書く場合を想像してみます。 ハリー・ポッターを知らない人に理解してもらうには、少なくともこの3点を伝える必要があります。
- ハリーは両親を亡くした孤児の少年
- 魔法学校で魔法を学ぶ
- ハリーの使命は悪の魔法使いと戦うこと
これらのポイントを含んだ文章を作ってみます。
【悪い例】 ハリー・ポッターは、両親を失った孤児の少年が魔法学校で仲間と共に学びながら、悪の魔法使いと戦う物語である。これはそんなハリーと友人たちの成長を描いた作品だ。
【良い例】 私は友達と協力することが好きな人間だ。そんな私とハリーは似ている。魔法の世界で学ぶハリーは、仲間の助けを借りながら強敵に立ち向かうが、私も何か問題に直面すると、いつも友達と協力して解決しようとしている。
【もう一つの良い例】 「友情こそが最強の魔法だ」という言葉が心に残った。両親を失い孤独だったハリーが、魔法学校で出会った仲間たちと共に成長し、悪に立ち向かう姿は、私に本当の強さとは何かを教えてくれた。
このように、単にあらすじを記すのではなく、自分の考えを述べた文章の中に、あらすじを織り交ぜます。
✅ あらすじセルフチェックリスト
- あらすじだけで1段落以上を使っていない
- 感想の中に自然にあらすじを織り込んでいる
- 本を知らない人でも最低限の内容がわかる
- 「私は〜」「僕は〜」のように自分の意見が中心になっている
- 読んでいない人が「続きが気になる」と思える書き方になっている
ステップ④:自分の意見や実体験を具体的に盛り込む
物語を読んでいると、「自分が主人公だったらこうするだろう」「主人公のこの発言は疑問だ」といったことを考えることがあります。それをそのまま書けば良いのです。
私がよく使っていた手法は、本の中に登場した文やセリフを引用し、それについて自分の意見を述べるというものです。
手順は以下のとおりです。
❶読んで感じたことを、思い浮かんだそのままの言葉で項目別にメモする 『ハリー・ポッター』を例にすると…
- ハリーは勇敢だ
- ハリーを支える友人たちが素晴らしい
- ヴォルデモートは恐ろしい悪役
- 自分も魔法を使ってみたい
- 特に透明マントと箒での空中飛行を体験したい
❷項目別にした自分の考えをひとつずつ発展させる 先ほど項目別にしたもののうち、「特に透明マントと箒で空を飛ぶことを経験したい」について具体的に説明したのが以下の文です。
私はなぜ「透明マント」を望んだのか考えてみます。透明マントを身につけると、周りを気にせず自由に動けるのが最大の魅力です。
次に「箒で空を飛ぶこと」を経験したいと思った理由として最初に思い浮かんだのは、高所から景色を眺めて、普段の心配事から逃れたいから、というものです。
しかし実際の世界には魔法は存在しません。透明マントも飛行する箒もありません。だから私は透明マントがなくても問題ないように、堂々と自分らしく振る舞う勇気を身につけなければなりませんし、箒で空を飛べたら…なんて思わなくても済むように、もっと現実に向き合いながら課題を解決していかなければなりません。
このように、箇条書きで挙げた文章を展開していきます。他の箇条書きも同様に展開していき、できた文章を組み合わせれば、読書感想文の基盤は完成です。
どれを使うか迷ったときは、以下の点を考慮して選びましょう。
- 読んでみてどの箇所が最も印象に残ったのか?→なぜ印象に残ったのか?
- この本を通して何を感じたか?
- この本から何を得たか?
- この読書経験を自分の日常にどう反映するか?
読書感想文をスムーズに書き進めるための3つの工夫
少しの工夫で、読書感想文はとても書きやすくなります。以下の方法を試してみてください。
工夫①:心が動いた箇所に付箋を貼る
本を読んでいるときに感じたことを、読み終わったときに忘れてしまうことがあります。それを防ぐために、気になった箇所や心が動いた箇所に付箋を貼るのがおすすめです。
「ハラハラする」「すごい」「自分にも似た経験がある」と感じた箇所に付箋を貼ります。可能なら、そのときの気持ちを付箋にメモしておくと、後で思い出しやすくなります。
工夫②:子どもと話しながら感想を引き出す
子どもだけで感想をまとめるのが難しいときは、付箋を参考に子どもと本の内容について話してみましょう。その中で、子どもが感じたことを引き出せます。
【具体的な質問例】
- 「主人公のどんなところが好き?」
- 「もし自分が主人公だったら、どうする?」
- 「この場面で何を感じた?」
- 「一番印象に残ったのはどこ?」
子どもの答えを紙に書き出していくと、読書感想文の全体像が見えてきます。
工夫③:「あとがき」も読む
「あとがき」がある場合は、読んでおくことをおすすめします。あとがきには、作品全体のまとめや作者が伝えたかったことが簡潔にまとめられています。あとがきを読むと、読書感想文を書くときのヒントを得られるかもしれません。
マル秘テクニック:課題図書の中からノンフィクション作品を選ぶ
毎年夏になると、読書感想文の課題図書が発表されます。学年ごとに複数の本が選ばれます。
? 最新の課題図書はこちら: 全国学校図書館協議会|課題図書一覧
その中でもノンフィクションは読みやすく、感想文が書きやすいため、宿題をこなすという意味では特におすすめです。
保護者のサポートは、子どもの実情に合わせて対応することが大切
読書感想文に書く内容を充実させる上で、最も取り組みやすいのは、読んだ内容について親子で話すことです。これで書きたいことを膨らませることができれば、後が楽になります。その内容を子どもがメモできれば理想的ですが、難しい場合もあります。そのときは、保護者がメモしてあげるなどのサポートも必要です。
子どもによってはさらにサポートが必要な場合もあります。その場合は、子どもの実情に応じて支援してあげてください。
文字や文章を書くのが難しい書字障害がある場合などは、保護者がサポートしても難しいこともあります。その場合は、読書感想文で必要以上に苦しむことのないように、先生と相談して読書感想文自体を免除してもらうなどの特別な配慮をしてもらうことも必要です。
まとめ
? 読書感想文完成前チェックリスト
- タイトルに工夫がある
- 冒頭文で読み手を引き込める
- 「〜と思う」を避けて表現できている
- あらすじが長すぎない
- 自分の体験や意見を具体的に盛り込んでいる
- 保護者と話しながら感想を広げられた
読書感想文は、ただの宿題ではありません。本との出会いを通じて、自分自身を見つめ直す貴重な機会です。
成功の鍵は本選びから始まります。自分の体験や興味に関連した本を選べば、書きたいことが自然にあふれ出します。
独創的なタイトル、「〜と思う」を使わない表現、最小限のあらすじ、そして実体験の織り込み。この4つのステップを実践すれば、誰でも魅力的な感想文が書けます。
付箋を活用し、親子で対話しながら進めれば、苦手意識も克服できるはずです。今年の夏は、読書感想文を楽しむ夏にしてみませんか。
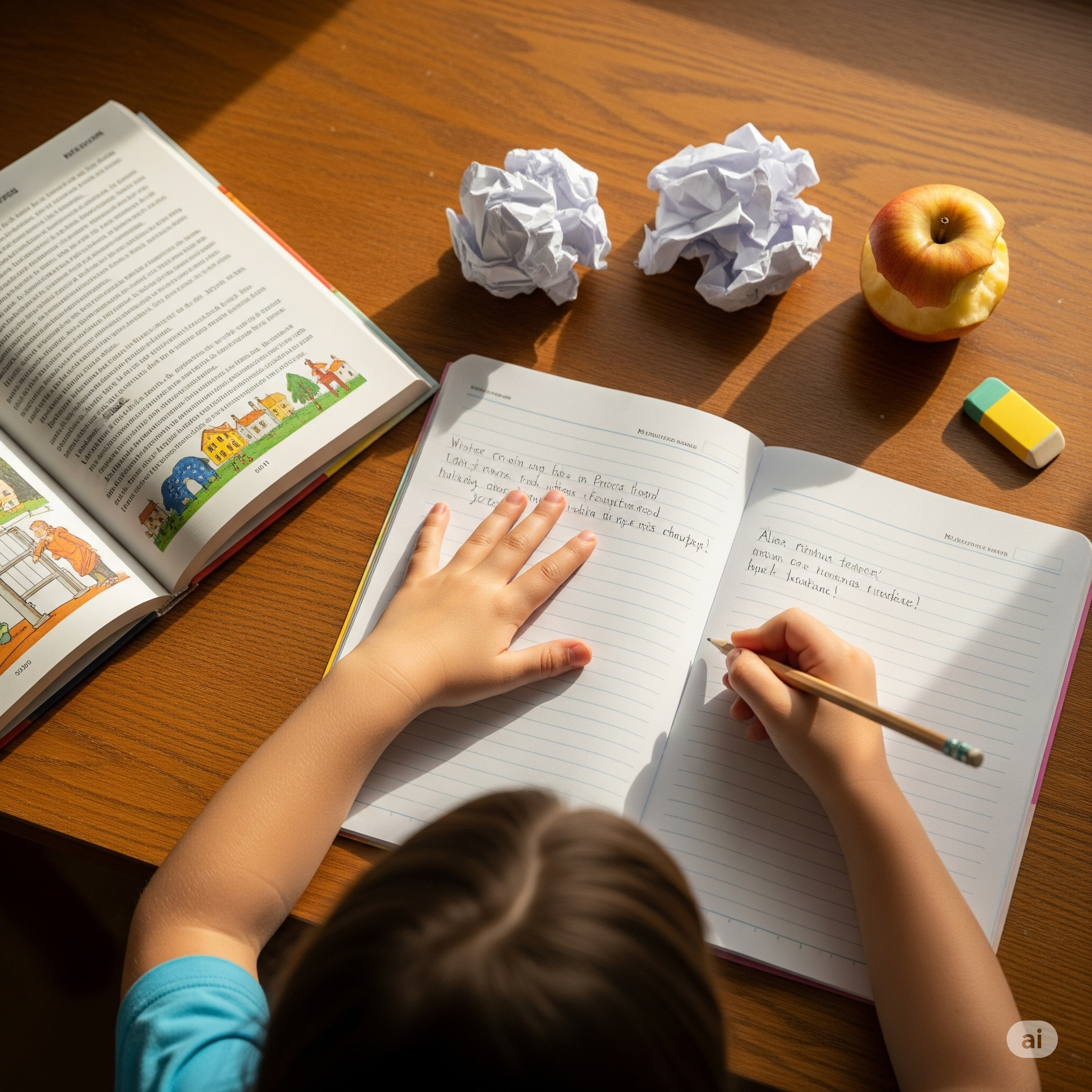


コメント